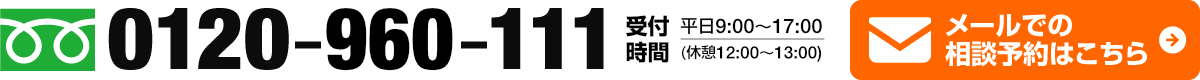1 はじめに

交通事故の被害は、車両の損傷による物損(物的損害)と怪我による人損(人身損害)とに分けられます。
交通事故は人身事故よりも物損事故の方が数としては多く、青森シティ法律事務所でも物損事故の被害に関するご相談・ご依頼を数多くお受けしております。
今回のコラムでは、物損事故をテーマにお話しいたします。
2 請求できる損害項目
物損事故の被害に遭った場合、以下のような損害項目の賠償を請求することができます。
(1)車両修理費
車両の損傷には、分損と全損があります。
全損とは、車両の修理が物理的に不可能な状態にまで損傷を受けた物理的全損と、車両修理費が車両時価額を超える経済的全損があります。
分損とは、車両の修理が物理的に可能であり、車両修理費が車両時価額を超えないことを言います。
分損の場合には、適正な金額の車両修理費の賠償を請求することができます。
(2)車両時価額・買替諸費用
全損の場合には、車両時価額に買替諸費用を加えた金額の賠償を請求することができます。
車両時価額は、同じ車種・年式・グレード、同程度の使用状態・走行距離など、同条件の車両を中古車市場で取得するための価額が基準となります。
レッドブック(オートガイド自動車価格月報)を用いることが多いですが、グーネット、カーセンサーネットなどの中古車販売サイトの検索結果を参照することもあります。
買替諸費用は、検査登録、車庫証明、廃車の法定費用、検査登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用、納車手数料、自動車取得税、リサイクル預託金などの請求が可能です。
(3)評価損(格落ち損害)
評価損(格落ち損害)とは、車両の修理をしても機能や外観に欠陥が残存し、あるいは事故歴・修復歴があること自体により車両の市場価値が低下してしまうことを言います。
機能や外観に欠陥を残すものについては、評価損の請求が認められやすいです。
一方で、事故歴・修復歴により商品価値が低下するものについては、①車種、②登録年数、③走行距離、④損傷の部位・程度、⑤購入時の価格、⑥中古車市場における通常価格などを考慮し、評価損の請求の可否が判断されます。
裁判例の傾向によれば、外国車・国産人気車種であれば初度登録から6年・走行距離6万km以内、それ以外の国産車であれば初度登録から3年・走行距離4万km以内の場合には、評価損の請求が認められやすいでしょう。
評価損の金額は、①車種、②登録年数、③走行距離、④損傷の部位・程度、⑤購入時の価格、⑥中古車市場における通常価格などを考慮し、算出されることが多いです。
裁判例によれば、修理費の10%~30%程度が認められていることが多いように見受けられます。
この点、評価損の金額を証明する資料として、ディーラーの下取り査定書や財団法人自動車査定協会の事故減価額証明書を取得することが有効ですが、裁判所の判断は必ずしもこれらの査定書・証明書に拘束されるものではありません。
(4)代車使用料(レンタカー代)
車両の修理・買替が終わるまでの間に代車(レンタカー)を使用する必要があった場合には、代車使用料(レンタカー代)の賠償請求が認められます。
代車使用料を請求するためには、代車の必要性(代車がなければ日常生活や通勤などに支障があること)が要件となります。
バスや電車などの公共交通機関やタクシーの利用では不便が大きいと言えることが必要であり、ご自身やご家族が他の車両を保有しているため代車を借りる必要がない場合には代車使用料の賠償は認められません。
また、代車使用料の請求が認められるのは、車両の修理・買替に必要な相当期間分に限られます。
代車の車種・グレードについても、必ずしも事故車両と同等のものである必要はないと考えられており、高級車を使用した場合には賠償が一部認められないこともあります。
本当に高級車でなければいけないかという点は、慎重に検討する必要があるでしょう。
(5)休車損(休車損害)
トラックやタクシーなどの営業車が損傷した場合、修理・買替に必要な期間の営業ができなくなり、営業損失が発生することがあります。
このような営業損失のことを休車損(休車損害)と言います。
休車損の請求が認められるためには、①事故車両を営業のために使用する必要があること、②代車を容易に調達することができないこと、③遊休車(代替車両)が存在しないこと、が要件となります。
また、休車損の金額は、事故車両の1日当たりの利益に休車日数を掛けることにより算出されます。
休車期間は、修理・買替に必要となる合理的期間に限られます。
事故車両の1日当たりの利益は、事故車両の売上高から、燃料代、修繕費、有料道路通行料などの変動経費を差し引くことにより算出します。
3 加害者が無保険の場合の対応
加害者が自動車保険(任意保険)に加入している場合、損害賠償金は保険会社から支払われます。
一方で、加害者が無保険の場合、人損に対しては自賠責保険から最低限の水準の補償が受けられるものの、物損に対しては自賠責保険からの補償が一切なく、加害者本人に対し賠償請求するしかありません。
この点、無保険で自動車を運転する人は、十分な資力がないことも多く、知性・常識・誠意に欠ける人物であることが常ですから、ご自身で請求を行っても回収が難儀することが想定されます。
しかし、弁護士が介入して損害賠償を請求する旨の書面送付をし、裁判手続を経て預金や給与を差し押さえるなどの対応をとることにより、回収に成功する例もあります。
回収が成功するかどうかはケースバイケースであり、弁護士を付ければ必ず回収できるという保証はありませんが、お困りの場合には弁護士にご相談・ご依頼いただくことを検討されるとよいでしょう。
4 弁護士費用特約の活用
物損事故では回収が見込まれる賠償金の額が少なく、弁護士に依頼する費用の方が多くかかってしまう「費用倒れ」の懸念をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、費用倒れの問題は、自動車保険の弁護士費用特約を利用することができれば、解決することができます。
弁護士費用特約は、自動車保険に附帯できる特約であり、交通事故の被害による損害賠償請求に関し、弁護士にご相談・ご依頼いただく場合の費用を保険会社が負担してくれるというものです。
ご自身が加入する自動車保険、ご家族が加入する自動車保険、あるいは交通事故時に同乗していた車両の自動車保険に弁護士費用特約が附帯されていないか、ご確認されることをお勧めいたします。
弁護士費用特約は、契約車以外の車両での交通事故や歩行中の事故、配偶者・同居親族や別居の未婚の子ども、家族以外の契約車の同乗者などにも適用できることが多いですので(ただし、保険会社により適用範囲が異なることもあります)、利用の可否を保険会社にご確認いただくとよいでしょう。
5 弁護士にご相談ください
物損事故の被害についてお困りの方がいらっしゃいましたら、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士にご依頼いただくことにより、面倒な手続対応を弁護士に一任することができますし、適正な賠償金の獲得や過失割合に関する争いの解決を期待することができます。
また、自動車保険の弁護士費用特約を利用すれば、経済的負担なく弁護士にご相談・ご依頼いただくことが可能です。
青森シティ法律事務所では、これまでに、物損事故を含む交通事故のご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
対応経験・解決実績が豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談ください。
(弁護士・木村哲也)