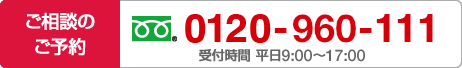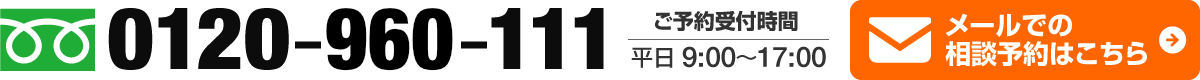青森シティ法律事務所では、離婚に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
離婚の条件として、財産分与が問題となることは少なくありません。
今回のコラムでは、離婚における財産分与について、ご説明させていただきます。
1 財産分与とは
財産分与とは、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚時に夫婦で分配することを言います。
財産分与は、離婚における金銭的条件のひとつとして、離婚の時に取り決めをするのが通常です。
離婚した後に財産分与を請求することもできますが、財産分与を請求する権利は離婚から2年以内に請求しなければ消滅してしまいます。
2 財産分与の対象財産
財産分与は、結婚したあとに夫婦が協力して築き上げたすべての財産が対象となります。
このような財産を夫婦共有財産と言います。
夫婦共有財産というのは、夫婦共有名義という意味ではなく、夫婦の一方の単独名義であったとしても、結婚したあとに夫婦が協力して築き上げた財産は、夫婦共有財産として財産分与の対象となります。
一方で、結婚する前から所有していた個人の財産、相続等で親から引き継いだ財産などは、財産分与対象にはなりません。
このような財産を特有財産と言います。
財産分与では、現金、預貯金、不動産、自動車、生命保険、有価証券、退職金など、あらゆるプラスの財産(資産)が対象となります。
住宅ローン、自動車ローン、その他のマイナスの財産(借金)についても、上記のようなプラスの財産の額からマイナスの財産の額を差し引いた差額を基準に分与する、という意味では財産分与の対象となります(ただし、ギャンブルや浪費などで一方が勝手に作った借金は、財産分与の対象となりません)。
例えば、プラスの財産が800万円、マイナスの財産が200万円であれば、差し引き600万円が財産分与の対象となり、後述の2分の1ルールに従えば、夫婦双方が300万円ずつ取得することとなります。
しかし、マイナスの財産の方が多いような場合には、マイナス分を折半する、という財産分与は行われないのが通常です。
例えば、離婚時にプラスの財産がなく、夫に500万円の借金があるとしても、妻が夫の借金のうち250万円を負担するべき(あるいは、妻が夫に対して250万円を支払うべき)ということにはなりません。
ただし、これはあくまで裁判における判断基準であり、協議や調停において、妻が夫の借金を折半して負担することに同意するのであれば、妻が肩代わりすることが禁じられるわけではありません。
3 財産分与の基準時
財産分与を行う際に、どの時点における財産を対象とするか、という問題があります。
夫婦が別居状態となり、離婚に至るまでに一定の年月が経過しているような場合には、別居開始時と離婚時とで夫婦双方の財産が変動していることがあるためです。
このような財産分与の基準時としては、夫婦の協力関係が失われた時点とするものと考えられています。
上記のように、財産分与とは夫婦が協力して築き上げた財産を分配する制度ですから、そのような夫婦の協力関係が失われた時点を基準時とすべきである、という結論になるのです。
そして、夫婦の協力関係が失われた時点という意味では、夫婦が不仲の末に別居に至ったのであれば、別居開始時が財産分与の基準時と判断されることが多いでしょう。
しかし、たとえ夫婦が別々に暮らしていたとしても、夫婦の協力関係が失われていなければ、財産分与の基準時であるとは判断されないでしょう。
例えば、単身赴任の場合には、一般的に、単身赴任期間中も夫婦の協力関係が継続していると考えられます。
そこで、具体的に夫婦の協力関係が失われた時点として、夫婦の一方が離婚を切り出した時点や、夫婦双方が離婚することに合意した時点をもって、財産分与の基準時とするなどの判断が考えられるでしょう。
4 財産分与の割合
財産分与の割合は、基本的には5:5で分けることとなります。
これを2分の1ルールと言います。
ただし、2分の1ルールは、裁判になった場合の判断基準であり、夫婦双方が合意すれば、5:5以外の比率で財産分与を行っても問題はありません。
また、2分の1ルールは裁判における絶対のルールというわけではなく、例外もあります。
会社経営者や医師であるなど、夫婦の一方が極端に多額の収入を得ることにより財産が形成されたような事案では、2分の1ルールが適用されないこともあります。
5 弁護士にご相談ください
以上のように、財産分与には、複雑な問題点がいくつもあります。
離婚と財産分与の問題について適正な解決を図るためには、法律の専門家である弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
青森シティ法律事務所の弁護士は、離婚と財産分与の問題について、多数の対応経験と豊富な解決実績がございます。
離婚と財産分与についてお困りの方は、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談いただければと存じます。
(弁護士・木村哲也)