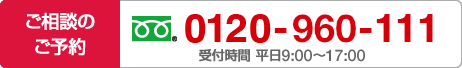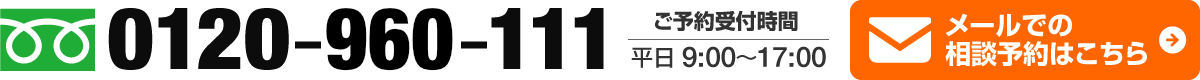青森シティ法律事務所では、交通事故の被害に関するご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
今回のコラムでは、交通事故における後遺障害等級の認定手続について、ご説明させていただきます。
1 後遺障害とは
交通事故でお怪我をされた場合、治療を受けることにより怪我が完治すればよいのですが、治療が一通り終わっても完治せずに心身に障害が残ってしまうことがあります。
これを後遺障害と言います。
交通事故による後遺障害は、症状固定(治療を継続してもこれ以上の改善が見込めなくなった状態)に至ったあと、自賠責保険会社を通じて申請をし、症状の程度に応じて1級ないし14級の等級認定を受けるという手続を踏むことになります。
1級が最も重篤な後遺障害であり、14級が最も軽微な後遺障害です。
心身に残った症状の内容・程度や治療の経過によっては、症状が今後長期間にわたって継続するものではないとみなされ、「非該当」の認定を受けることもあります。
2 等級認定の重要性
後遺障害等級の認定結果いかんにより、交通事故の被害者の方が受け取ることのできる賠償金の額には、大きな差が出てきます。
そのため、適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要となってきます。
後遺障害に対する損害賠償としては、主に、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料とがあります。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が原因でこれまでどおりに仕事ができなくなることによる将来の収入の減少を賠償するものです。
後遺障害逸失利益は、被害者の方の年収額に対し、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率を掛け、さらに、後遺障害が原因で収入の減少を被るであろう期間(年数)をカウントして算出します。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛を金銭で評価して賠償するものです。
1級から14級までの後遺障害等級に対応する労働能力喪失率の標準値と後遺障害慰謝料の標準額は、以下の表のとおりとなります。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率(標準値) | 後遺障害慰謝料(標準額) |
|---|---|---|
|
1級
|
100%
|
2800万円
|
|
2級
|
100%
|
2370万円
|
|
3級
|
100%
|
1990万円
|
|
4級
|
92%
|
1670万円
|
|
5級
|
79%
|
1400万円
|
|
6級
|
67%
|
1180万円
|
|
7級
|
56%
|
1000万円
|
|
8級
|
45%
|
830万円
|
|
9級
|
35%
|
690万円
|
|
10級
|
27%
|
550万円
|
|
11級
|
20%
|
420万円
|
|
12級
|
14%
|
290万円
|
|
13級
|
9%
|
180万円
|
|
14級
|
5%
|
110万円
|
後遺障害がどの等級に該当するかにより、労働能力喪失率、後遺障害慰謝料とも、相当の差が生じてきます。
その結果、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の合計額としては、数百万円ないし数千万円単位での差が出てくるのです。
適正な金額の賠償金を受け取るためには、適正な後遺障害等級の認定を受けることが必要不可欠です。
3 事前認定と被害者請求
後遺障害等級の認定を受けるためには、症状固定(治療を継続してもこれ以上の改善が見込めなくなった状態)に至ったあと、自賠責保険会社を通じて、自賠責損害調査事務所に申請を行うこととなります。
後遺障害等級の認定手続には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
「事前認定」とは、加害者側の保険会社が後遺障害等級の認定申請の手続をすべて代行してくれるものです。
「被害者請求」とは、交通事故の被害者の側から、自賠責保険会社に対し、直接、後遺障害等級の認定申請を行うものです。
この点、後遺障害等級の認定申請を行うためには、自賠責保険金の支払請求書、交通事故の発生状況を記載した事故状況説明図などを作成し、後遺障害診断書、治療中の各月の診断書・診療報酬明細書、レントゲン・MRI・CTなどの各種画像資料、各種検査結果、その他各種必要書類を収集・添付して、自賠責保険会社へ提出する必要があります。
被害者請求の場合には、このような後遺障害等級の認定手続を、交通事故の被害者の側で行わなければなりません。
一方で、事前認定の場合には、加害者側の保険会社がこのような後遺障害等級の認定申請を代行してくれるため、手間がかからず、便利であると思われるかもしれません。
しかし、加害者側の保険会社が適正な後遺障害等級の認定のために積極的に動いてくれるわけではなく、かえって、交通事故の被害者にとって不利な内容の意見書(例えば、交通事故の被害者が訴える症状について、詐病であるとか、交通事故とは無関係の持病であるなどと主張する意見書)を顧問の医師に作成させて添付し、適正な後遺障害等級の認定を妨害してくる実態も存在します。
後遺障害等級の認定において不利な結果が出されてしまうと、賠償金の額が大きく減じられるという不利益は計り知れませんので、手続の透明性を確保するために、被害者請求を選択するべきです。
そして、被害者請求による後遺障害等級の認定申請を行う場合には、専門家である弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。
被害者請求による後遺障害等級の認定申請を弁護士にご依頼いただくことで、手続への対応のために強いられる手間と時間の負担を弁護士に一任することができます。
また、交通事故に詳しい弁護士であれば、適正な後遺障害等級の認定を受けるために必要な画像資料や検査結果についてアドバイスするなど、戦略的に後遺障害等級の認定申請を進めていくことが可能です。
4 異議申立て
後遺障害等級の認定申請をし、認定結果が出された場合でも、その認定結果に不服であるということもあります。
このように、後遺障害等級の認定結果に不服がある場合には、異議申立てを行うことが可能です。
そして、異議申立てにおける主張が正当であると判断されれば、後遺障害等級の格上げなどの変更がなされます。
後遺障害がどの等級に該当するかにより、受け取ることができる賠償金の額が大きく変わってきますので、認定結果に不服があるのであれば、積極的に異議申立てを検討していくべきでしょう。
異議申立てに当たっては、ただ闇雲に不満なところを主張するだけでは、後遺障害等級の格上げなどの成果を得ることは期待できません。
適正と考える後遺障害等級の認定基準を正しく理解し、その認定基準に該当すると認めるに足りる主張を展開することが必要ですし、新たなレントゲン・MRI・CTなどの画像撮影、医師による鑑定意見書の作成などが必要となることも多々あります。
後遺障害等級の認定結果に対する異議申立ては、非常に複雑で専門的な領域であるため、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただいたうえで、対応をご検討されることをお勧めいたします。
5 弁護士にご相談ください
交通事故における後遺障害等級の認定手続は、適正な金額の賠償金を受け取るために、非常に重要な手続です。
適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、加害者側の保険会社の言うままに委ねるのではなく、まずは弁護士にご相談いただければと存じます。
そして、後遺障害等級の認定申請は、適切な治療を継続することを前提に、必要な画像の撮影や検査の実施、適切な内容の後遺障害診断書を主治医に作成してもらうことなど、治療中の段階から治療終了段階まで、注意すべきポイントが多々あります。
そのため、交通事故の発生直後のタイミングから、交通事故に精通した弁護士にご相談・ご依頼いただくのがベストの対応です。
青森シティ法律事務所の弁護士は、交通事故に関するご相談・ご依頼を多数お受けし、解決してきた実績が豊富にございます。
被害者請求による後遺障害の適正等級の認定、異議申立てによる認定等級の格上げなど、多くの経験と実績がありますので、ぜひ一度、お気軽に青森シティ法律事務所にご相談ください。
(弁護士・木村哲也)