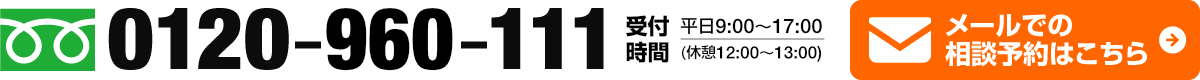1 寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について「特別の寄与」をした共同相続人がいる場合に、その者の本来の相続分に一定の加算をすることで、相続人間の実質的な公平を図る制度です。
例えば、
・被相続人(親)の家業に無給で従事して、財産を増やした
・長期にわたり、被相続人(親)の介護をし、介護費用の支出を抑えた
以上のような場合には、寄与分の問題が生じる可能性があります。
本コラムでは、遺産分割における寄与分に関して、その成立要件や成立した場合の計算・処理について解説いたします。
2 寄与分がある場合の相続分の計算
以下のような、具体例で考えてみます。
【例】被相続人の遺産が1億円である。相続人は、子である兄弟2人であり、兄が無給で家業に従事し、被相続人の財産形成に2000万円の「特別の寄与」があった。
●寄与分として処理しない場合
兄の相続分:1億円×1/2=5000万円
弟の相続分:1億円×1/2=5000万円
遺産1億円のうち、2000万円は、兄の無償の努力により財産形成がされたものといえます。
しかしながら、寄与分として処理しなければ、形式的に相続分が定められるため、兄の家業従事は、文字通りのタダ働きとなります。
その結果、財産形成に寄与した兄と、財産形成に寄与していない弟との間で、実質的な不公平が生じてしまいます。
そこで、兄は、「寄与分」として、2000万円あることを主張することができます。
●寄与分として処理する場合
みなし相続財産:1億円(遺産)-2000万円(兄の寄与分)=8000万円
兄の相続分:8000万円×1/2+2000万円=6000万円
弟の相続分:8000万円×1/2=4000万円
このようにして、兄の特別の寄与によって形成された財産を寄与分として考慮することで、結果として、相続人間の公平が図られることになります。
3 寄与分の成立要件
寄与分が成立するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
①相続人による寄与であること。
②「特別の寄与」(通常の扶養義務の範囲を超える程度のもの)といえること。
③被相続人の財産が形成・維持されたこと。
④寄与行為と財産の形成・維持との因果関係があること。
⑤相続開始時(被相続人の死亡時)までの寄与であること。
上記5つの要件を満たすことで、寄与分の主張が可能となります。
なお、要件①に関し、相続人以外の親族が特別の寄与を主張した場合には、平成30年民法改正により、「特別の寄与の制度」が新設されましたので、そちらを活用することになります。
4 寄与分の具体例
(1)家業従事型
被相続人の事業に関し、相続人が労務を提供した場合に認められる類型です。
農業や自家営業を夫婦・親子で協力して行った場合が典型例です。
もっとも、すでに述べたように、「特別の寄与」と評価される程度の従事が必要です。
詳しい要件などは、下で詳しくご説明します。
(2)金銭等出資型
被相続人に対して、財産権または財産的な価値のある利益を与えた場合に認められる類型です。
具体的には、金銭を交付したり、物の所有権を移転したり、不動産を無償で使用させたりした場合が該当します。
契約に基づいて行われた給付に関して、当該契約に基づいて返還を請求できる場合には、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与があったとはいえず、寄与分は認められません。
例えば、被相続人の借金を相続人が立て替えて支払ってあげた場合において、被相続人が相続人に対し、分割で立替金を返還する約束がある場合には、金銭出資型の寄与分は認められません。
(3)療養看護型
病気療養中の被相続人を介護した場合に認められる類型です。
もっとも、単に介護したというだけではなく、当該療養介護によって、被相続人が介護費用の支出を免れたなどの財産上の効果がもたらされた場合のみ、寄与分が認められます。
詳しい要件などは、下で詳しくご説明します。
(4)扶養型
被相続人の生活費を援助していた場合に認められる類型です。
もっとも、親族であれば、法律上の扶養義務を負っており、その範囲内のものにすぎない場合には、寄与分は認められません。
すなわち、扶養型の寄与分が認められるためには、法律上予定されている扶養義務を上回る程度の扶養を行う必要があります。
(5)財産管理型
被相続人が所有する財産を管理した場合に認められる類型です。
例えば、相続人が被相続人の賃貸不動産を管理したことによって、被相続人が管理費用の支出を免れた場合がこの類型に該当します。
他には、被相続人が所有していた土地の売却にあたり、借家人の立退交渉、家屋の取壊し、滅失登記手続、売買契約の締結等を行った際に、寄与分が認められた例があります。
5 寄与分が問題となりやすいもの
ここでは、寄与分が問題となりやすい、家業従事型の類型と療養看護型の類型について、細かくみていきます。
(1)家業従事型
【家業従事型の寄与分の要件】
①相続人による家業従事であること
寄与分が認められるのは、相続人による家業従事に限られます。
なお、相続人以外の親族が被相続人の家業に従事した場合には、相続人に対し、特別寄与料の請求できる可能性があります。
②労務の内容が特別の貢献と評価できる程度のものであること
家業の従事が手伝い程度ではなく、従事すべき仕事として携わっていたことが必要です。
③家業従事が相当期間継続していること
明確な基準はありませんが、少なくとも3~4年は継続している必要があるといわれています。
④家業従事が無償あるいは著しく少額で行われていたこと
完全に無償である必要はありませんが、通常の給料水準と同等の対価を受け取っていた場合には、寄与分は認められません。
⑤相続人による家業従事の結果、財産の維持・増加がされたこと
以上のような条件を満たした家業従事寄与によって、被相続人の財産が維持・増加されたことが必要となります。
【家事従事による寄与分を主張するための証拠】
・経営内容のわかる資料(確定申告書等)
・給与の支払い状況がわかる資料(給与台帳、給与明細書、確定申告書等)
・報告書(家計の状況、労務提供状況、労務内容等を明らかにするもの)
※請求を基礎づけるために適切な証拠は、事案によって異なるため、個々の事案に応じたオーダーメードの証拠の収集・提出が必要となります。
【家事従事による寄与分の金額】
寄与分の金額は、法律上、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して」定めることとされています。
一応の目安として、以下の計算式があります。
寄与者の受けるべき相続開始時の年間給与額×(1-生活費控除割合)×寄与年数
寄与者の受けるべき相続開始時の年間給与額は、相続開始時の賃金センサスをもとに算出されることが多いです。
生活費相当額を控除するのは、無償(に近い給与のもと)で家業に従事していた場合、通常は、相続人の実質的な生活費が家業収入の中から支出されているからです。
具体的な生活費相当額が分かればそれによりますが、分からない場合には一切の事情を考慮の上概算額によることになります。
(2)療養看護型
【療養看護型の寄与分の要件】
①相続人による介護であること
寄与分が認められるのは、相続人による介護に限られます。
なお、相続人以外の親族が被相続人の介護をした場合には、相続人に対し、特別寄与料の請求できる可能性があります。
②被相続人に療養看護の必要性が認められること
疾病や高齢による動作困難等の療養看護の必要性が認められる必要があります。
個別の事情にもよりますが、一般には認知症であったり、要介護2以上だったりしたことが必要とされています。
なお、被相続人が要介護2以上の認定がされていたとしても、入院・入所の期間は、基本的には療養看護の必要性は認められません。
③介護の内容が特別の貢献と評価できる程度のものであること
介護の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。
そこで、通常であれば第三者に有償で委任するような行為である必要があるともいわれています。
本来ならば施設入所や入院等が必要であるにもかかわらず、相続人が自宅で介護した場合が典型例です。
④介護が相当期間継続していること
おおむね1年以上の介護が必要とされていますが、個別の事情により長短することがあります。
⑤介護が無償あるいは著しく少額で行われていたこと
完全に無償である必要はありませんが、通常の介護報酬水準と同等の対価を受け取っていた場合には、寄与分は認められません。
⑥相続人による療養介護の結果、財産の維持・増加がされたこと
以上のような条件を満たした療養介護寄与によって、被相続人の財産が維持・増加されたことが必要となります。
単に、被相続人の話し相手になるなど、精神的な安心感を与えただけでは、この要件は満たしません。
【療養看護による寄与分を主張するための証拠】
・被相続人の症状がわかる資料(要介護認定通知書・要介護認定資料等)
・被相続人が必要とする介護内容を明らかにする資料(介護サービス利用票・ケアプラン・施設利用契約書・介護利用契約書等)
・介護期間がわかる資料(医療記録等)
・相続人が行った介護内容を明らかにする資料(写真、日記、手紙等)
※請求を基礎づけるために適切な証拠は、事案によって異なるため、個々の事案に応じたオーダーメードの証拠の収集・提出が必要となります。
【療養看護による寄与分の金額】
療養看護による寄与分の算定に関しても、計算式が存在します。
報酬相当額(日額)×介護日数×裁量割合
報酬相当額は、介護保険制度で要介護度に応じて定められている介護報酬基準額が参考にされることがあり、おおむね6000円から9000円の範囲で計算されます。
また、介護報酬基準は、基本的に、看護または介護の資格を有している者への報酬を前提としていることから、裁量割合による調整がされることが多いです。
裁量割合は、0.5から0.8程度の間で適宜修正されています。
6 弁護士にご相談ください
どのような場合に寄与分が認められるか、認められるとしてどの範囲で認められるか、その額はいくらかなど、寄与分に関しては、複雑かつ難解な判断が求められることがあります。
寄与分がある場合には、相続人間の不公平感を背景に、遺産分割の話し合いが円滑に進まない場合も少なくありません。
寄与分をはじめとする遺産分割問題でお悩みの方は、青森シティ法律事務所の弁護士にご相談ください。
(弁護士・一戸皓樹)